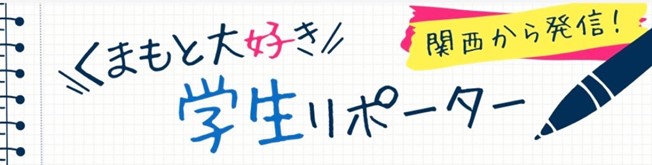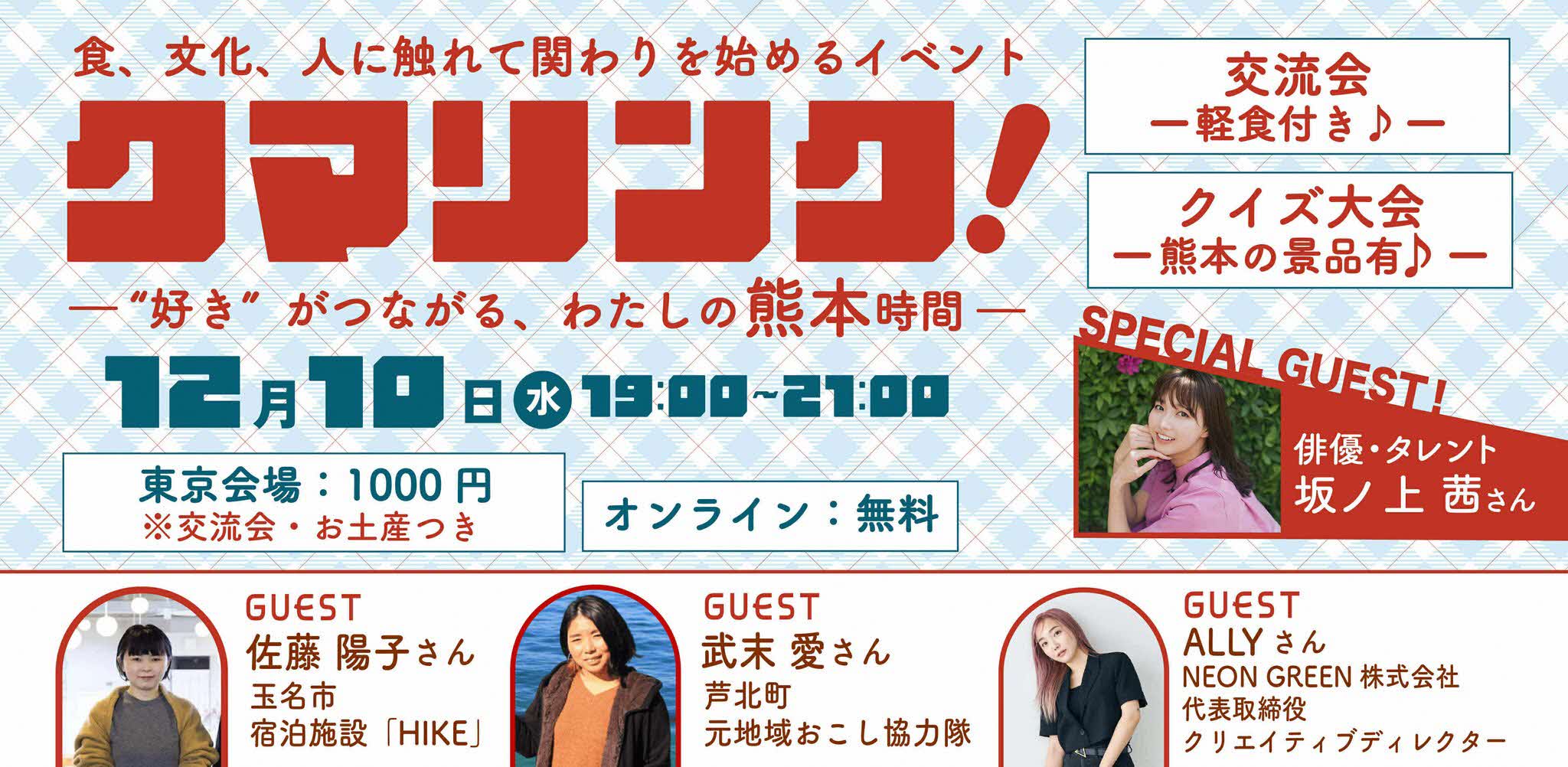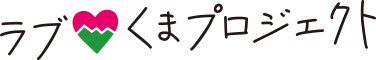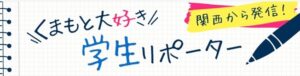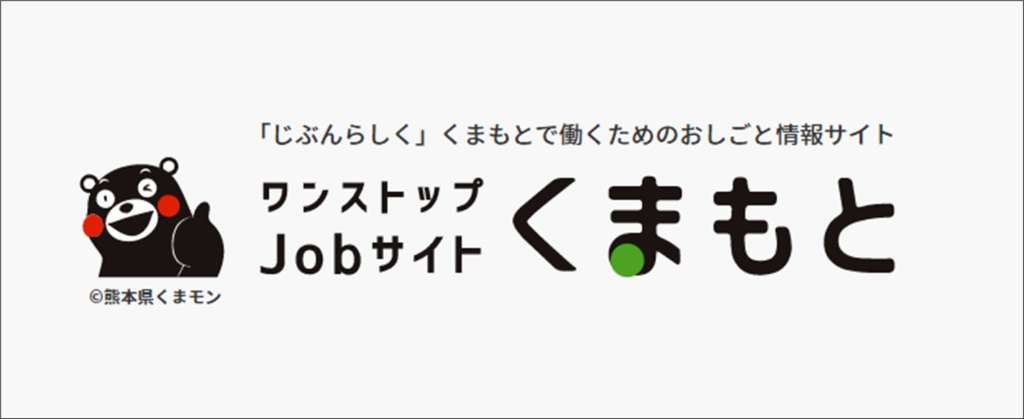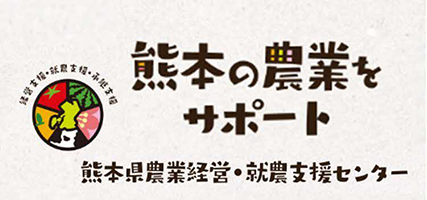旬感くまもと
五感を刺激するレジャーアイランド“天草”
天草地方は八代海と有明海に囲まれた大小約120の島々から成り、豊かな自然と独自の文化が息づく地域です。南蛮文化やキリシタンの歴史を伝える施設が点在し、天草市には、2018年に世界文化遺産に登録された河浦町の“天草の﨑津集落”内にゴシック様式の﨑津教会があります。また、同市内の五和町周辺では、ミナミハンドウイルカが群れで生息していて、船で沖合を泳ぐイルカを観察できるイルカウォッチングは、遭遇率9割を超えます。
グルメでは、ウニや車エビ、タイをはじめとする海の幸のほか、日本最大級の地鶏「天草大王」を刺身やタタキで味わえるのも地元ならではです。さらに、新鮮な具材と豚骨や鶏ガラなどで取った優しいスープが特長の地域のソウルフード「天草ちゃんぽん」も外せません。歴史文化、自然、味覚のすべてを満喫できるのが天草の魅力です。


■一般社団法人 天草宝島観光協会
| 所在地 | 熊本県天草市中央新町15-7 |
|---|---|
| 問い合わせ先 | 0969-22-2243 |
| HP | https://www.t-island.jp/ |
地域に根ざして発展してきた天草陶磁器
さまざまな魅力に満ちた天草ですが、実は陶磁器の原料である陶石の国内最大の産地でもあります。その生産量は、全国生産量の約8割を占めるといわれています。天草陶石の特長は、その色の白さや単独でも成形可能な可塑性といった質の高さ。そのため、全国的に有名な有田焼や波佐見焼にも使われていて、日本の陶磁器の発展に大きく貢献してきました。
また、良質の陶石が採れることから、天草市や隣接する市町には、多くの窯元が点在しています。その一つが天草市本渡町にある「水の平焼」で、創業260年の歴史を誇ります。初代・岡部常兵衛から受け継ぐ海鼠釉(なまこゆう)の技術を用いて生活雑器、花器、茶道具などを製作しています。
特長である海鼠釉は2種類の釉薬を塗り重ねることで、斑文や流文などの独特な柄を生み出します。水の平焼の海鼠釉には青海鼠と赤海鼠の2種類があり、赤海鼠は5代目・源四郎が開発し、以降改良を重ねて現在に至っている歴史ある技術です。




■水の平焼
| 所在地 | 熊本県天草市本渡町本戸馬場2004 |
|---|---|
| 問い合わせ先 | 0969-22-2440 |
| 営業時間 | 10:00~17:00 |
| 休み | 12/31、1/1(但し、個展やイベント出展等により不在の場合があります) |
天草を陶石の島から陶磁器の島へ
江戸時代から続く天草陶磁器ですが、それぞれの窯元が地域に根ざした生活雑器を作ってきたため、各窯元独自の作風が磨かれてきました。水の平焼8代目であると同時に、現在、天草陶磁器の島づくり協議会の会長も務める岡部さんも、「天草の多様な窯元の作品に触れれば、きっと自分のお気に入りが見つかると思います。それが天草陶磁器の魅力」と語ります。
同協議会は、今年21回目を数える天草大陶磁器展の実行委員会を母体として、同展に限らず年間を通して天草陶磁器発展のために各窯元が共に活動していくことを目的に、2018年に発足しました。今年の同展は、10月31日から5日間の予定で開催。それに先立つ9月27日には、熊本市中心市街地のびぷれす広場でプレイベントが実施され、天草各地の窯元が自慢の作品の展示即売を行います。また、天草の窯元には、同展の期間以外でも作陶体験ができるところがあるので、「天草窯元めぐり」のホームページ(https://amakusatoujiki.com/)をチェックしてみてください。マリンレジャーだけではない魅力を感じに、ぜひ天草へ足を運んでみませんか。




■天草陶磁器の島づくり協議会(天草市役所産業政策課内)
| 所在地 | 〒864-0002 熊本県荒尾市万田1560-1 |
|---|---|
| 問い合わせ先(TEL) | 0969-23-1111 |
| HP | https://amakusatoujiki.com/aca/ |